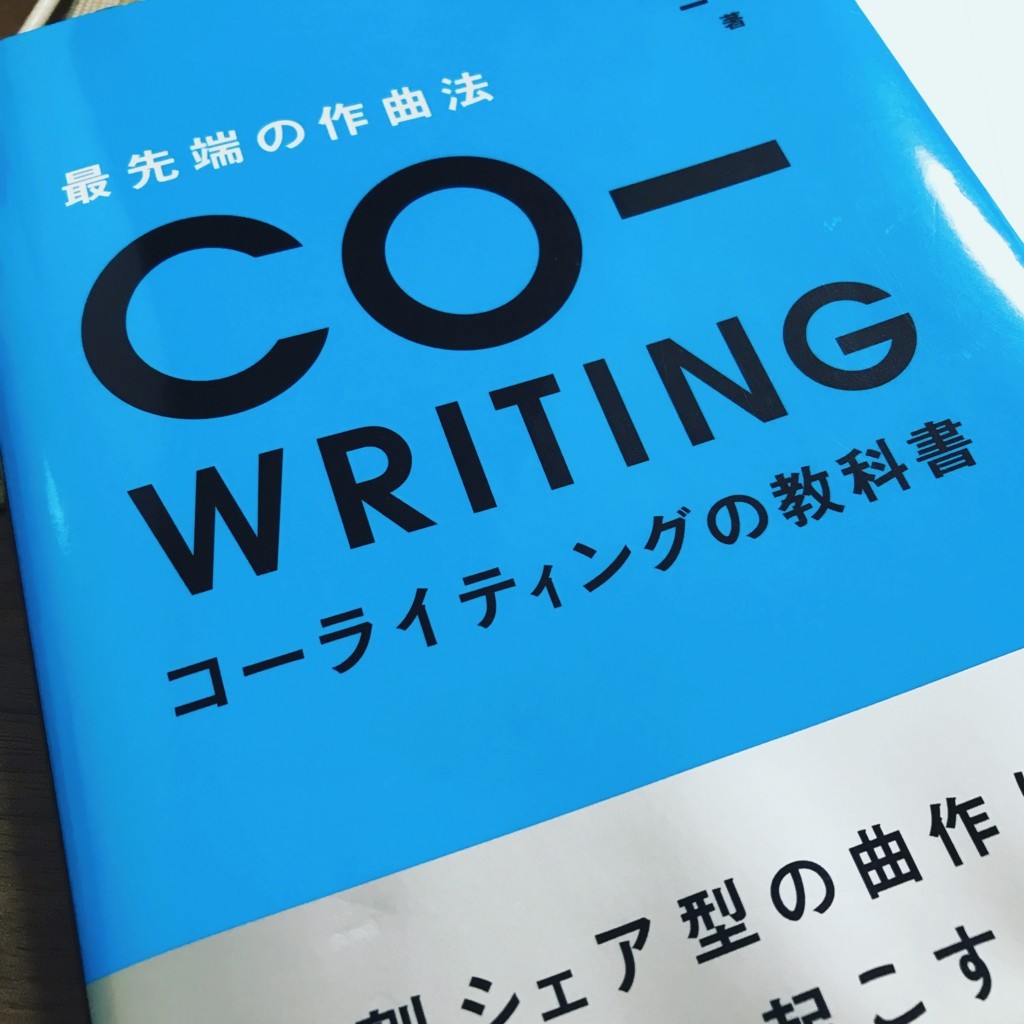こんにちは、作曲家のペンギンスです。前回に引き続きBLUE BOOKこと「コーライティングの教科書」を紹介していきたいと思います。
黒船を引き合いに出すまでもなく日本人は外圧を受けて変わるのが得意です。なにがしかの外国由来のアイテムやら慣習やらがなだれ込んでくると、潜在的に抱えていた問題を「この際だから」と一気に改善する。作曲の世界でも、本書に書かれているようなグローバル・スタンダードのコーライト・ルール(「他メンバーの責任分野にも積極的に意見を出すことでケミストリーを起こす」とか「印税は必ず等分で」とか)を持ち込むことで、色々な国内の作曲家が抱える問題を解決するきっかけになればいいなと思っています。いわばショック療法ですね。
例えば、作曲→編曲、とウォーターフォール型(順送りに、段階を追ってものづくりを進める方式)で制作を進めて行くと、編曲段階で洋楽的な洗練されたトラックを作ろうとしても、作曲段階でガッチガチのABサビ形式で頻繁にコードチェンジするJ-POP的なものがあがってくると、そこからはいかようにも直し難いという問題が発生すると思います。
この場合、最初からコーライトを取り入れてみるとどうなるか。「アレンジャーが作曲にも積極的に意見を出す」ことで、「完パケまで見据えたソングライティング」が可能になり、これがJ-POPのともすれば膠着状態に陥った構成に風穴を開ける可能性があると思います。
また、コーライト否定論の根拠になりがちな「印税を等分したら稼ぎが少なくなるから日本の小さなマーケットにコーライトは馴染まず非現実的」という意見についても、コーライトを奇貨とすることで以下のようなきっかけにすればよいと思っています。(そもそも日本はアメリカにつぐ世界2位の音楽マーケットなのですが・・・)
1.印税を等分したら稼ぎが少なくなるのはその通り。となると自ずから「採用曲数を増やす」か「アレンジャーとして編曲料で稼ぐ」か、はたまた「そもそも海外で通用する作家になるか」の三択を迫られます。これを機にコーライティングを活用して制作曲数を大幅に増やすことで稼ぐか、アレンジのレベルを上げて編曲ごとお買い上げいただくか、海外に飛び出すか決断する良い機会なのではないでしょうか。(ちなみに僕は1の道に進みつつ、3を狙っています)
2.コーライトはある意味組織でのものづくりなので、これまでの曲作りでどうしても軽視されがちだった「効率」の問題をクリエイターに突きつけていると思います。「もっと効率よくやらないとねー」と言っているだけでは一生効率はあがりません。1曲あたりの印税が割り算で減るという現実を突きつけて初めて、「ミックスにここまで時間かけるのは無駄じゃないか」とか「もっと早く歌詞を書く方法はないものか」などといった、普通のメーカー(製造業)が当たり前にやっている生産効率の向上に目が向くことになればいいなと思っています。見ていると、無駄が多すぎます。
クリエイティブな仕事だから仕方ない?ちょっと待ってください。すごくオシャレな服とかかっこいいビルだって、どこかのメーカーが効率を突き詰めて考えて作っているわけじゃないですか。音楽だけ、好きに時間をかけていいはずがありません。音楽家は音楽のことを特別扱いしすぎだと思います。せっかく70億人も人が住んでる地球に生まれたんだから、自分の曲をiPhoneやコカ・コーラぐらい売りまくりたいじゃないですか。効率よく、ヒットファクトリーになりましょう。
自分がそうだからよくわかるのですが、DAWが普及したいま、作曲はマジで孤独な作業です。バンドのレコーディングのような風景を想像している一般の方が作曲家の仕事風景をみたら本気で「社会と関わり合いを絶ったハッカーが音楽を聴きながら、なんか怖いことしてる」ぐらいにしか見えないかもしれません。それくらい作曲は孤独な作業になってしまいました。そんな制作の日々に風穴をあけるだけでも、コーライトには大きな意味があると思っています。人と会わず誰の意見も聞かず部屋のアーロンチェアーと体が溶けて一体化してしまう前に、コーライトしましょう!

最先端の作曲法 コーライティングの教科書 役割シェア型の曲作りが、化学反応を起こす!
- 作者: 伊藤涼,山口哲一
- 出版社/メーカー: リットーミュージック
- 発売日: 2015/04/17
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る